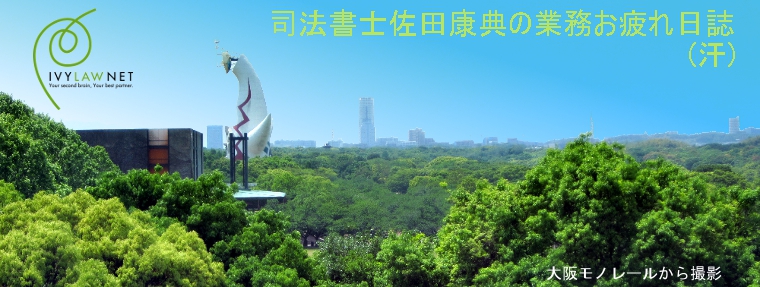1月22日最高裁判決以前の準備書面
1月22日の最高裁判決以前、再貸付による取引の分断と消滅時効を主張していた相手方への反論内容です(準備書面から一部抜き出しています)。この最高裁判決とぴったり沿った内容になっていたのでほっとしました。
準備書面抜粋
1 取引の個別性についての反論
被告は平成15年7月18日最高裁判決をはじめ、同年9月11日、同年同月16日付の最高裁判決引用し、本件各貸付と返済については各個別取引であり、利息においても一回ごとの貸付額で利息制限法を適用すべきであるとしているが、明らかに誤りである。同7月18日最判において、被告は当事者の合理的意思を配慮したかのように述べているが、実際には最高裁は推認できる借主の合理的な意志を重視したのであり、事実「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付とその返済が繰り返される金銭消費貸借取引においては、借主は借入の総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられることから、弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果当該借入金債務が完済され、これに対する債務の弁済の指定が無意味となる場合には特段の事情がない限り、弁済当時存在する他の借入金債務に対する弁済を指定したものと推認することができる」と判示した。さらに利息制限法の潜脱を目的とした被告が原審で主張していた民法136条2項ただし書の適用についても「法1条1項1号及び2条に規定は金銭消費貸借上の貸主には、借主が実際に利用することが可能な貸付額とその利用期間を基礎とする法所定の制限内の利息の取得のみを認め、上記各規定が適用される限りにおいては、民法136条2項ただし書の規定の適用を排除する趣旨と解すべき」として、貸主の期限利益は保護ざれないものとして、各貸付に対する返済期限までの利息の収受を認めなかったのである。本最高裁判決は本件と同様に、基本契約に基づいて手形貸付が数口並存して行われていた事案であり、民法136条2項ただし書を根拠にした被告の各貸付の返済期限までの利息を収受できる旨の主張に対し、借主が実際に利用できる金額の限度でしか利息の収受を認めないとする強行法規である利息制限法の基本原則を踏まえ、借主の合理的な意思を推認して即時充当の結論を導き出したのである。
(中略)
平成19年6月7日最高裁判決は、「各基本契約は同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払金が発生した場合には、上記過払金を、弁済当時存在する他の借入金に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する合意を含んでいるものと解するのが相当である」とし、やはり借主の合理的な意思を推認し、過払金発生後の後発の借入に対する即時充当を認めている(もっとも、平成19年7月17日最高裁判決によれば、必ずしも基本契約がなくても継続的な金銭消費貸借取引が行われていた場合においても同様の即時充当の結論を導いている)。
(中略)
1 後の貸付金にも充当される
昭和52年6月20日最高裁第2小法廷判決は,550万円の借入を必要とする借主に対し2口合計1100万円を貸し付け,うち600万円を即時両建拘束預金とした事案で,「右取引条件の故に実質金利が利息制限法1条1項所定の利率を超過する結果を生じ,ひいては遅延損害金の実質的割合も同法4条1項所定の割合を超過する結果を生じてしまっている以上,右超過部分は,同法の法意に照らし違法なものとして是正しなければならない」「その方法としては,前記各即時両建預金が存在しているため実質金利が利息制限法に違反する結果を生じていた期間中,本件貸付契約中利率及び遅延損害金の割合に関する約定の一部が無効になるものとして是正するのが相当であり,上告人が支払った利息のうち実質貸付額550万円を元本として利息制限法1条1項を超過した部分は,民法488条又は489条により,本件貸付契約又は本件別口貸付契約の残存元本債務に充当されたものと解するのが相当である。」と判示し,本来なら借りないで済んだ超過貸付額を差し引いた実質貸付額についてのみ利息が発生するとした。
同判決が「超過部分は,同法の法意に照らし違法なものとして是正しなければならない」と利息制限法の強行法規性から導かれる違法是正機能を実質貸付理論の根拠としている以上,過払い状態となった後,これを秘匿して返さないで貸し付けた超過貸付に対し利息を取ることも是正されなければならず,借りないで済んだ超過貸付額を差し引いた,すなわち充当後の実質貸付額についてのみ利息が発生することとなる。過払い後に貸付けに際して交付される金員は,不当利得金が貸金業者の手元に拘束されずに返還されていたとすれば借りないで済んだ金額であり,超過貸付として実質貸付額から差引かれるべきものであって実質貸付額ではない。
2 被告の時効の主張について
(1)仮に被告の主張するとおり,本件の取引がAの取引とBの取引に 分かれるとしても,Aの取引によって生じた過払い金はB取引が継続 している間は消滅時効は進行しない。いったん過払い金が発生しても,これがその後の貸付にかかる債務に充当される可能性がある状態が継続することになるから,それぞれが完済扱いとなったり,あるいは原告のほうで以後の追加貸付けを断念して明確に取引を終了させて過払い金返還請求をするなどしない限り取引継続中の個々の過払い金返還請求権の消滅時効は進行しないのである。したがって本件のAの取引の過払い金及び利息金の支払い請求権は時効消滅していない。
2009年2月5日 1:57 PM | カテゴリー:未分類 | コメント (0)