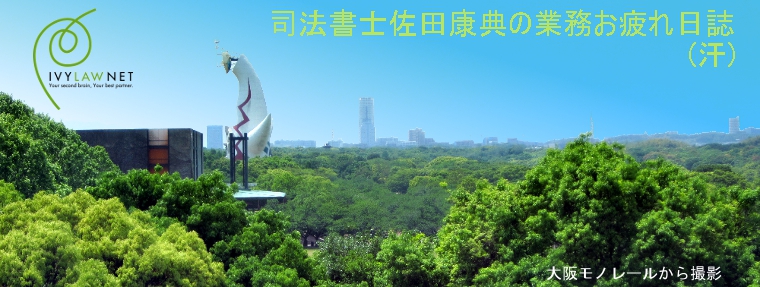日本文学専攻おいらはドラマー
今でこそ法律関係の仕事をしていますが、大学では何を隠そう日本文学を専攻していました。また高校大学と結構ハードなロックバンド(同類の人たちは、クラシックロック、プログレッシブロックと呼んでいる範疇の音楽)のドラムとして、ライブにもたまには出てたりして、バンド活動を中心に学生生活をすごしていました。という訳でどんな学生生活を送っていたかは想像に難くないと思われます。とてもじゃないが、ほめられたもんじゃ、ありません。今まであんまり実務に関すること以外書いてこなかったのですが、やはり、以前から心がむずむずして、もう我慢できないので、それらの分野でも感じていることを書かせていただこうとうと思います。
まずは文学のほうから
最近、村上春樹の1Q84BOOK3 10月−12月を発売当日に購入し、休日や仕事の合間の電車での移動時間を利用して数日で読み終えました。
予め断っておきたいのですが、私の大学のゼミでも当時から村上春樹は人気があり、親しかった友人を含め、数人が村上春樹の小説論を専攻して研究していました。ですから、巷には、村上春樹のフアンという範疇に止まらず、半分研究者のつもり、ぐらいの人が、「ハンパネェー」ほど多数居るはずです。そこを踏まえ、あえて一切の私見に対するご意見・反論を受けつけず、感想を述べてみたいとおもいます。
読み終えて、実は結構感動しました、もしかして、村上ワールドの「完成型」かもしれないと感じたのです。初期の風の歌を聴け、初期の羊をめぐる冒険等ほか多数の初期の作品では「直子」という愛する女性と「鼠」という親友を失った喪失感・悲しみがテーマだったと思います。根底には、現実世界の不確かさに対する不安、現実世界の崩壊と再構築が作品で試行されていました。ですから、良く吉本隆明の「共同幻想論」がベースになった世界観=都市幻想という観点から、当時論文を書いている学生が多かったと記憶してます。現実の崩壊と言う観点では村上龍の「コインロッカーベイビーズ」や「限りなく透明に近いブルー」とも相通じるところありますね。当時だいたい、村上龍の作品が好きな人は村上春樹のフアンでもあったと思います。この喪失感に人間の記憶のはかなさ、悲しみ自体も薄れていくという時間の流れの中で、もう一度立ち上げっていこうする次の段階に踏み出した作品が「ノルウェイの森」だったと思います。(続く)
2010年12月27日 2:48 PM | カテゴリー:未分類 | コメント (0)